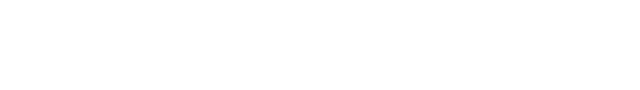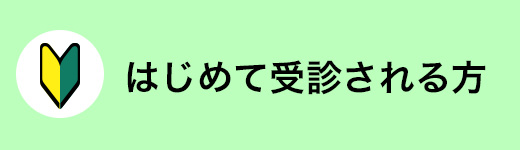高血圧について
1.高血圧とは
高血圧とは、血圧が慢性的に正常範囲を超えて高くなる状態を指します。
血圧とは、心臓が血液を送り出す際に血管にかかる圧力のことで、通常「収縮期血圧(上の血圧)」と「拡張期血圧(下の血圧)」の2つの値で表されます。
日本高血圧学会では、正常血圧を収縮期血圧120mmHg未満かつ拡張期血圧80mmHg未満と定義し、収縮期血圧120~139mmHgまたは拡張期血圧80~89mmHgの範囲を「高血圧予備軍(正常高値血圧)」としています。
高血圧は140/90mmHg以上と定義され、動脈硬化を進行させ、脳卒中や心筋梗塞などの重大な疾患のリスクを高めます。
自覚症状が少ないため、定期的な血圧測定が重要です。
2.高血圧の症状
高血圧は多くの場合、無症状で進行します。
しかし、血圧が高くなると頭痛、めまい、動悸、肩こり、耳鳴りなどの症状が現れることがあります。
血圧が急激に上昇すると、頭痛や吐き気、視力低下といった症状が出ることもあります。長期間にわたり高血圧が続くと、血管が硬くなり(動脈硬化)、心臓や脳、腎臓に負担がかかります。
重症化すると、脳卒中や心筋梗塞、心不全、腎不全など命に関わる病気を引き起こすこともあります。特に、早朝や寒冷時に血圧が上がりやすいため、冬場や起床時の血圧管理が重要です。
症状がなくても、定期的に血圧を測定し、高血圧が疑われる場合は早めに受診しましょう。
3.高血圧の検査
高血圧の診断には、まず血圧測定を行います。
診察室で測る「診察室血圧」と、自宅で測る「家庭血圧」があり、家庭血圧が135/85mmHg以上の場合も高血圧と診断されます。自宅での測定は、朝起床後と就寝前の決まった時間に測ることが推奨されます。
血圧が高い場合、原因を調べるために血液検査や尿検査、心電図、眼底検査、エコー検査などを行うことがあります。特に、若年者や急に血圧が上がった場合、ホルモン異常や腎臓病などの「二次性高血圧」の可能性もあるため、詳しい検査が必要になることがあります。
診察時には生活習慣や家族歴も確認し、総合的に評価します。
4.高血圧の治療について
高血圧の治療は、まず生活習慣の改善から始めます。
塩分を控えた食事(1日6g未満が目標)、適度な運動(ウォーキングや軽い筋トレ)、ストレス管理、禁煙、節酒が重要です。
特に塩分は血圧に影響を与えやすいため、減塩を意識しましょう。生活習慣の改善で十分に血圧が下がらない場合は、降圧薬を使用します。
薬の種類や量は個人の状態に応じて決定され、長期間の継続が必要です。
高血圧のコントロールが困難な場合や、精密検査が必要な場合には、近隣の専門診療科のある総合病院を紹介します。
5.高血圧の治療薬の種類と解説
高血圧の治療薬には、大きく分けて以下の種類があります。
① 利尿薬:尿の排出を促し、血液量を減らして血圧を下げます。
② カルシウム拮抗薬:血管を広げて血圧を下げる薬で、第一選択薬としてよく使用されます。
③ ARB(アンジオテンシンII受容体拮抗薬)・ACE阻害薬:血管を収縮させる物質の作用を抑え、血圧を下げます。
④ β遮断薬:心拍数を減少させ、血圧を下げる働きがあります。
⑤ α遮断薬:血管を広げる作用があり、特に男性の前立腺肥大を伴う高血圧に使用されます。
患者さんの年齢や合併症、生活習慣に応じて適切な薬が処方されます。
6.最新の治療について
近年、高血圧治療の進歩により、より効果的な降圧薬や治療法が登場しています。例えば、従来の薬を組み合わせた配合薬が開発され、1錠で複数の作用を持つことで服薬の負担を減らすことができます。また、腎デナベーション療法(カテーテルを用いた血圧治療)が研究されており、薬が効きにくい難治性高血圧の治療法として期待されています。さらに、スマートウォッチなどのデバイスを活用した血圧管理も注目されており、リアルタイムで血圧の変動を把握できる技術が進んでいます。これらの最新治療は、今後の高血圧管理に大きな影響を与えると考えられています。