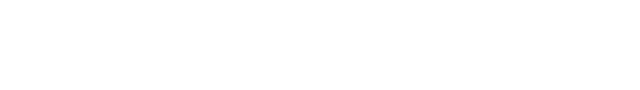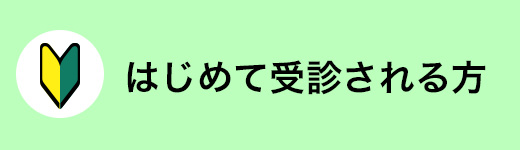脂質異常症(高脂血症)について
1.脂質異常症とは
脂質異常症(高脂血症)とは、血液中の脂質(コレステロールや中性脂肪)が正常範囲を超えて多くなり、動脈硬化を引き起こしやすくなる病気です。
特に「LDL(悪玉)コレステロールが高い」「HDL(善玉)コレステロールが低い」「中性脂肪が高い」の3つのパターンがあります。
脂質異常症は自覚症状がほとんどなく、気づかないうちに進行するため「サイレントキラー」とも呼ばれます。
この状態が続くと、動脈硬化が進み、心筋梗塞や脳梗塞といった重大な疾患のリスクが高まります。原因としては、食生活、運動不足、遺伝(体質)、ストレスなどが関係しており、生活習慣の改善や適切な治療によって予防・管理することが重要です。
2.脂質異常症の症状
脂質異常症は、多くの場合自覚症状がありません。
そのため、健康診断や血液検査を受けなければ気づかないことがほとんどです。
しかし、長期間放置すると、動脈硬化が進行し、血管が狭くなったり詰まったりすることで、胸の痛み(狭心症)や突然のしびれ・麻痺(脳梗塞)などの症状・疾患を引き起こすことがあります。
特に家族に脂質異常症の人がいる場合や、肥満・高血圧・糖尿病などのリスクがある人は注意が必要です。
自覚症状がないからこそ、定期的な検査で早期発見し、適切に管理することが大切です。
3.脂質異常症の検査
脂質異常症の診断には、血液検査を行います。
特に重要な指標は「LDL(悪玉)コレステロール」「HDL(善玉)コレステロール」「中性脂肪(トリグリセリド)」の3つです。
LDLコレステロールが140mg/dL以上、中性脂肪が150mg/dL以上、HDLコレステロールが40mg/dL未満の場合、脂質異常症と診断される可能性があります。
さらに、動脈硬化の進行度を調べるために、動脈硬化度検査(ABI、CAVI;当院で検査可能)や頸動脈エコー検査(必要な場合は他院へ検査依頼)を行うこともあります。
健康診断で「コレステロールが高い」と言われた方は、詳しい検査を受けて、必要な治療を始めることが大切です。
4.脂質異常症の治療について
脂質異常症の治療の基本は、食事療法・運動療法・薬物療法の3つです。
食事療法では、揚げ物や加工食品を控え、魚・野菜・食物繊維を多く摂ることが大切です。
運動療法としては、ウォーキングや軽いジョギングなどの有酸素運動が有効です。
これらの生活習慣の改善だけでは十分な効果が得られない場合、スタチンやフィブラート系薬剤などの脂質を下げる薬を使用します。
脂質異常症は動脈硬化を防ぐための長期的な管理が必要な病気です。コントロールが難しい場合や精密検査が必要な場合には、近隣の専門診療科のある総合病院をご紹介いたします。定期的な診察を受けながら、将来の健康を維持していくために治療を続けましょう。
5.脂質異常症の治療薬の種類と解説
脂質異常症の治療薬は、血液中の脂質の種類や患者さんの状態に応じて選択されます。
スタチン系薬:LDLコレステロールを下げ、動脈硬化を抑える効果があり、最も一般的に使われます。
フィブラート系薬:中性脂肪を下げ、HDLコレステロールを増やす作用があり、特に高トリグリセリド血症の患者に適しています。
エゼチミブ:小腸でのコレステロール吸収を抑える薬で、スタチンと併用することが多いです。
PCSK9阻害薬:LDLコレステロールを強力に下げる注射薬で、特に家族性高コレステロール血症の患者に使用されます。
EPA製剤:魚由来の成分で、中性脂肪を下げる効果があり、動脈硬化の予防にも有効です。
それぞれの薬には特徴があり、副作用も異なりますので、状態に応じて最適な治療を提案いたします。